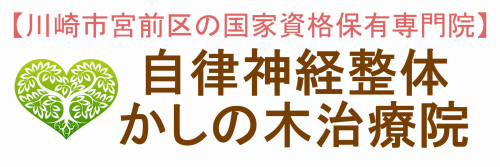症状別の自律神経整体とエッセイ

整体的食事の摂り方
背骨の異常には、間違った生活習慣によって起こる不調を見て取ることができます。
同様に食べ過ぎによる異常も観察することができます。
肥満や糖尿病を例に挙げるまでもなく、食べ過ぎは多くの病気や不調の原因になっています。
今、一番多い自律神経の乱れの原因は、内臓の働きを超えて食べる事=食べ過ぎです。
整体的観点では、食べ過ぎを量的なものと質的なものとに分けて考えています。
まず、量的に食べ過ぎた場合には、首の上の方(上部頚椎)の左側の緊張が強くなります。
さらに量的な食べ過ぎが習慣的に持続すると、交感神経の働きが低下します。
するとその影響で、背骨の一部に異常を起こし、不調を感じるようになります。
比較的多く見られる症状としては、左の偏頭痛、肩こり、倦怠感、眼精疲労、めまい、不整脈などです。
一方、糖分、脂肪分、アルコールなどの質的な食べ過ぎは、肝臓、腎臓、膵臓などに負担がかかります。
この質的な食べ過ぎを整体的にみると、まず首の上の方の右側の緊張が強くなります。
さらに食べ過ぎが続くと、副交感神経の働きが低下します。
背骨の弾力が低下し、身体の最も弱い部分から病気や不調を生じるようになります。
右の偏頭痛、吹き出物、ガン、体温の低下、腎臓の異常、腎性高血圧、糖尿病、膵炎、肝炎、痛風、インポテンツ、生理不順などが、よく起きる症状です。
最近では健康のために、健康食品やサプリメントなどの栄養補給食品や栄養価の高い食品を習慣的に摂取されている方も多いです。
また、健康法として1日2リットルの水を飲まれている方もいます。
しかし、〝過ぎたるは及ばざるがごとし〟という言葉があるように、身体に良いものでも必要以上に摂り過ぎれば、毒になります。
植物に水や肥料をあげ過ぎると、枯れてしまうのと同じです。
残念なことに、健康の為にと摂っている食品が原因で、身体を悪くしている事が多いのです。
元来、人類は何万年もの間、飢えや飢餓状態の中で子供を生み育ててきました。
そして、その中で身体を環境に適用させて、進化してきました。
消化吸収能力は、少しの栄養でも生きて行ける様に優れていますが、反対に排泄能力は、過剰な栄養に対応できる様になってはいません。
現在の日本は、かつて経験した事がない程の飽食社会です。
戦中、戦後では、食べ物の少ない中でも、重い荷物を何十キロと担いで運んだと聞きます。
また、当時は10人兄弟姉妹などは珍しくなく、女性は背負った赤子が泣くと乳を飲ませ、オムツを替えて野良仕事や夜鍋仕事を続けていました。
栄養が身体を養うことは周知の事実ですが、私達は同じような生活ができるでしょうか?
また子供を10人産めるでしょうか?
種族保存の生殖本能は、栄養の足りない時にこそ強く働くもので、飽食社会の中で生理機能には変化が起きています。
1+1が2になるのが物理学で、1+1がマイナス1になるのが人間の身体なのです。
一般的な栄養基準もありますが、体格や体質、生活習慣は人によって違いがあり、個人にそれを当てはめるには無理があります。
また、人間の身体は毎日違います。
身体にとって必要な栄養は、体調や運動量によっても変わり、計量できるものではありません。
・「1日3食、食べなければならない」ではなく、空腹を感じるなら食べる
・胃腸の働きが悪いときには、さっぱりしたものが食べたくなる
・汗をかいたときには、塩辛いものが食べたくなる
といった、できるだけ身体の声に耳を傾けた、バランスの良い食事内容を心掛けたいものです。
また、腹七分目を守った食生活を送ることが、整った自律神経を保つ上で大切なことです。
≫当院の自律神経整体について:自律神経失調症の整体